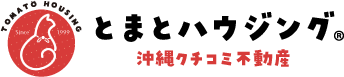いつもは自身でハンドルを握って走ることの多い国道58号線。
いつもより目線の高いバスの車窓から
北谷町~嘉手納町と、キャンプ瑞慶覧、嘉手納飛行場を眺めながら北上。
基地内に米軍のトラックがずらっと奥まで並んでるのが見える
かと思うと
フェンス沿いの樹木で隠れて見えなくなる
普段は車の走りとともにびゅんびゅん流れていく樹木は、
緑地としての役割ではなく
目隠しとして植えられているんだなと改めて思う
嘉手納飛行場となっているエリアは、地下水が豊富な田畑が広がっていたという
アメリカ統治下では、畑を基地にとられながらも耕作を続けるにはパスポートを持って自分の畑へ入ったという
↓
今も一部残る、黙認耕作地の成り立ちを知る
バスは読谷村へ
集団自決(そこにいた者、家族どうしで殺し合う)という凄惨な最期で多くの命が失われたがチビチリガマ
米軍に捕まると、殺されたり辱めをうける、それならば…という最期の選択をした
陽のあたる車道から、下へ下へとおりていくと慰霊の碑や鎮魂のための像が点在し、ガマの入口の前で
平和ガイド糸数慶子さんの話を静かに聞く
一方、同じ読谷村にあるシムクガマは、
チビチリガマのような凄惨な状況にはならなかった
そこにいたハワイ帰りの2名が、「アメリカ人は人を殺さないよ」と説得し
ガマにいた、およそ1000人は捕虜となり生きることを選んだ
2人の実経験による言葉だったからこそ、
(酷いことをされる)という
恐怖を乗り越えて米軍の捕虜になり、生きることを選択できたのだと感じる
80年後のそこは、ただの山の緑と流れる小川、自然でしかなかった
佐喜眞美術館には、そのチビチリガマとシムクガマの絵もある
ふたつのガマで起きたこと、その対比をさらにイメージとして考えることができる
屋上から、美術館のすぐ隣のフェンスから広がる普天間飛行場を眺める
あっち側(基地)とこっち側(わたしの生活圏)
米軍基地があることは認識している
「軍用地」と呼び、売買をしているわたしもいる
長年解決されない問題があり
事件事故が起こり、ニュースで知る
が、
無意識に
基地は、わたしの生活には関係ない場所となっている
今回のように
沖縄戦で起こったことの話を聞くことで
すぐそばにある基地の存在が現れる
関係ないことはない
ということを思い出していきたい